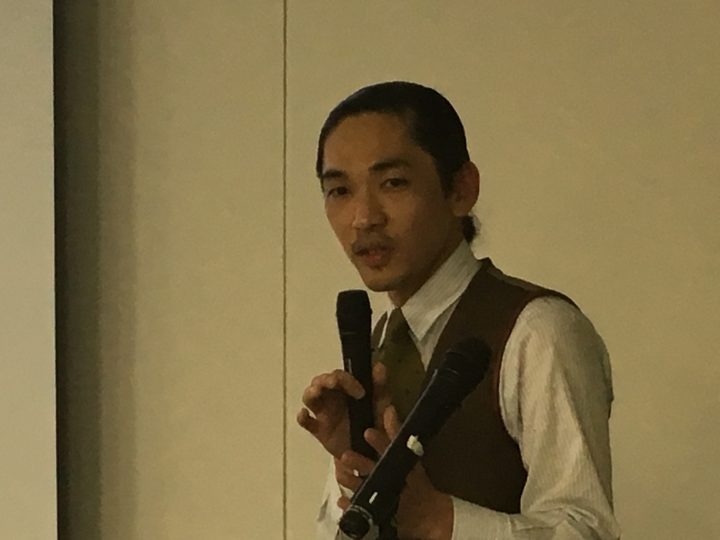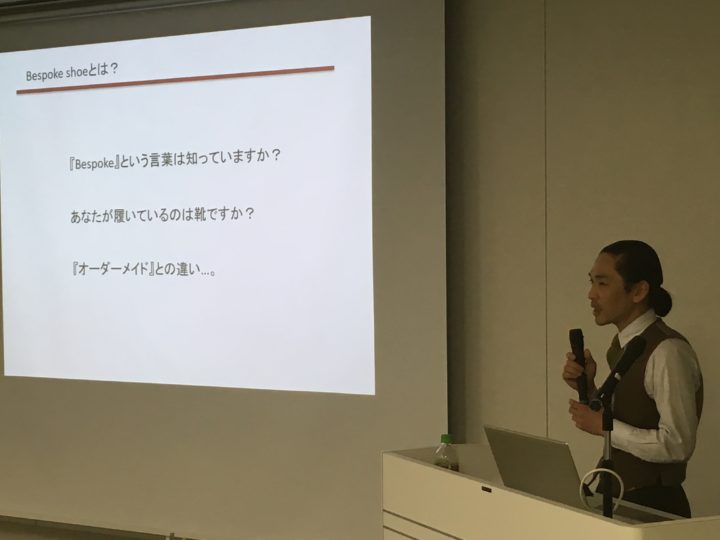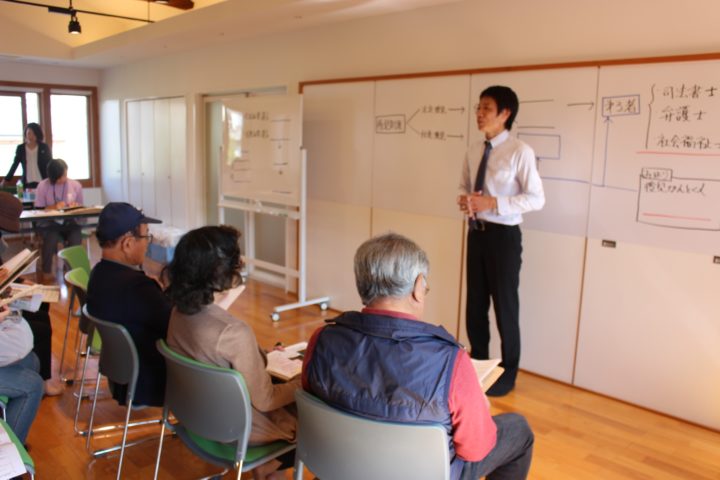経営数値を拒絶する経営者
経営者である以上、経営数値(業績数値)の最低限の知識は持つ必要があります。
業績管理は会計事務所任せ…といった会社に「利益をあげている(儲けている)」会社は存在しません。
特に中小零細企業にとって、日々の売上・経費・利益は、経営の舵取りに直結します。
なので、大枠の経営数値管理は、経営者の必須業務ということになります。
「私は数値に弱いから…」「経営分析などは分からないから…」と言われる経営者に時々会いますが、とてもリスキーです。
経営者として最低限知っていてほしい経営数値知識は…
①売上の意味(公式)
②粗利益率の意味(仕組み)
③固定費の最低限の種類(勘定科目)
④営業利益の意味
⑤損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)の仕組み
⑥損益分岐点の算出方法
⑦資金繰り表の仕組みと策定方法(自分で策定できるレベル)
⑧経営分析指標(自己資本比率、売上高経常利益率)
⑨簡易キャッシュフローの残高
⑩借入金の返済計画と月次キャッシュフロー計画
以上です。
これだけの知識とスキルを要すれば、あとは会計事務所とのリレーションができます。
毎月の月次決算(収支実績)は、会計事務所の仕事ではありません。会計事務所はあくまでも確認・相談機関です。
毎月いくらの収入があり、いくらの収益(儲け)ができ、いくらのキャッシュを使うことができるか?
零細企業からスタートする場合に、失敗(事業の断念)しないためにも、最低限の係数知識は身につけましょう。
経営者である以上、経営数値(業績数値)の最低限の知識は持つ必要があります。
業績管理は会計事務所任せ…といった会社に「利益をあげている(儲けている)」会社は存在しません。
特に中小零細企業にとって、日々の売上・経費・利益は、経営の舵取りに直結します。
なので、大枠の経営数値管理は、経営者の必須業務ということになります。
「私は数値に弱いから…」「経営分析などは分からないから…」と言われる経営者に時々会いますが、とてもリスキーです。
経営者として最低限知っていてほしい経営数値知識は…
①売上の意味(公式)
②粗利益率の意味(仕組み)
③固定費の最低限の種類(勘定科目)
④営業利益の意味
⑤損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)の仕組み
⑥損益分岐点の算出方法
⑦資金繰り表の仕組みと策定方法(自分で策定できるレベル)
⑧経営分析指標(自己資本比率、売上高経常利益率)
⑨簡易キャッシュフローの残高
⑩借入金の返済計画と月次キャッシュフロー計画
以上です。
これだけの知識とスキルを要すれば、あとは会計事務所とのリレーションができます。
毎月の月次決算(収支実績)は、会計事務所の仕事ではありません。会計事務所はあくまでも確認・相談機関です。
毎月いくらの収入があり、いくらの収益(儲け)ができ、いくらのキャッシュを使うことができるか?
零細企業からスタートする場合に、失敗(事業の断念)しないためにも、最低限の係数知識は身につけましょう。
投稿日: 2019年11月19日 | 7:11 pm