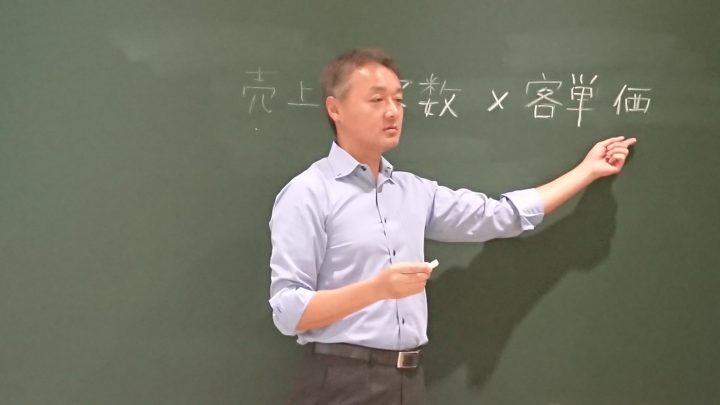コンサルタントは稼いでなんぼか??
サラリーマンコンサルタントだった頃の話…。
とあるクライアントとのコンサルティング支援顧問契約を成立し、上司に報告したところ。
自分:「◯◯◯株式会社様で、契約をもらいました。」
上司:「おめでとう。(…とここまでは良かったのですが)。それで、いくらで契約できたの??」
自分:「・・・・・・。」
普通、ホンモノのプロのコンサルタント同士だったら、「どんなコンサルティングを提供するの?」という質問が来ませんかね??
また、こんな経験もあります。クライアントの新商品の市場調査(アンケート)をしていた時。
某大手コンサルティング会社(F総研)の担当者:「コンサルタントの人ですか?」
自分:「はい、そうですが?中小企業診断士です。」
担当者:「その調査の仕事、いくらで引き受けていますか?」
会ってすぐの質問にしては、あまりにも不躾だと思いませんか?
以前の上司であれ、某大手コンサルティング会社の担当者にしろ、「稼いでなんぼだ!」というマインドに支配されているとしか思えません。
もちろん、コンサルティングは慈善事業(ボランティア)ではないですから、適正なフィー(報酬)をもらうことは必定です。
しかし、小生のような町医者型のコンサルタントとして、クライアントにできるだけ寄り添いたいと思っている者にとっては、とても違和感があります。
やはり、「極上のコンサルティングサービスを提供した先に、報酬がある」という、ギブ型のマインドだけは大切にしていきたいと思っています。
サラリーマンコンサルタントだった頃の話…。
とあるクライアントとのコンサルティング支援顧問契約を成立し、上司に報告したところ。
自分:「◯◯◯株式会社様で、契約をもらいました。」
上司:「おめでとう。(…とここまでは良かったのですが)。それで、いくらで契約できたの??」
自分:「・・・・・・。」
普通、ホンモノのプロのコンサルタント同士だったら、「どんなコンサルティングを提供するの?」という質問が来ませんかね??
また、こんな経験もあります。クライアントの新商品の市場調査(アンケート)をしていた時。
某大手コンサルティング会社(F総研)の担当者:「コンサルタントの人ですか?」
自分:「はい、そうですが?中小企業診断士です。」
担当者:「その調査の仕事、いくらで引き受けていますか?」
会ってすぐの質問にしては、あまりにも不躾だと思いませんか?
以前の上司であれ、某大手コンサルティング会社の担当者にしろ、「稼いでなんぼだ!」というマインドに支配されているとしか思えません。
もちろん、コンサルティングは慈善事業(ボランティア)ではないですから、適正なフィー(報酬)をもらうことは必定です。
しかし、小生のような町医者型のコンサルタントとして、クライアントにできるだけ寄り添いたいと思っている者にとっては、とても違和感があります。
やはり、「極上のコンサルティングサービスを提供した先に、報酬がある」という、ギブ型のマインドだけは大切にしていきたいと思っています。
投稿日: 2018年9月14日 | 1:00 am