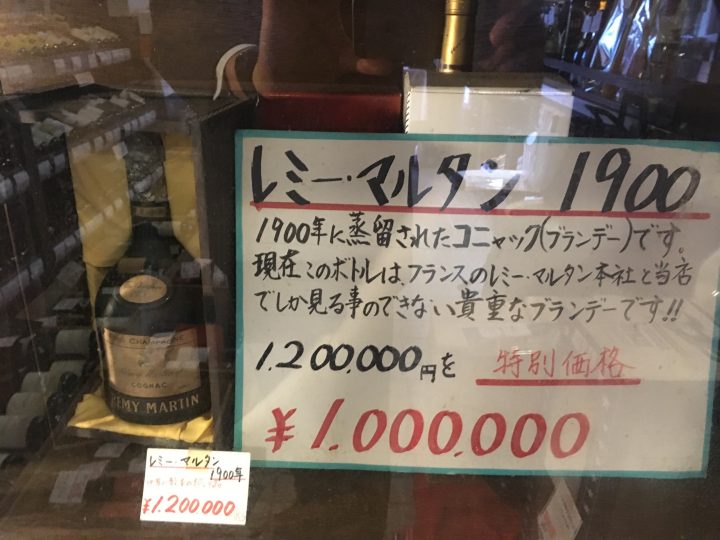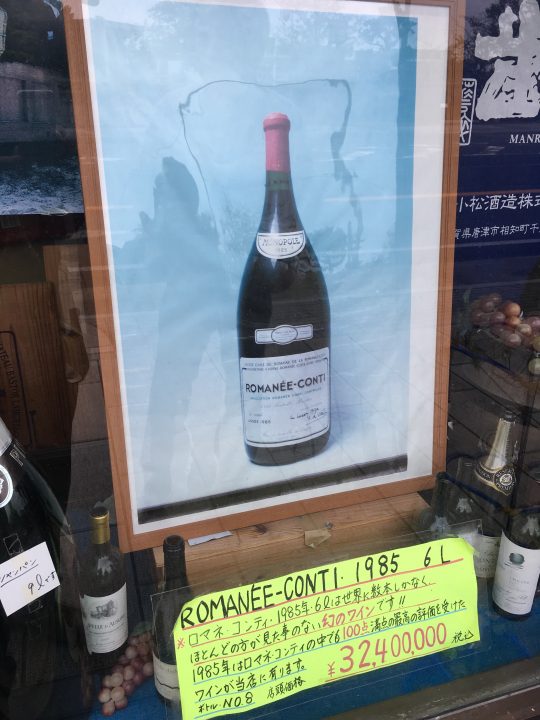アントレプレナー(起業家)へのエール〜月次決算・振り返りの必然性〜
起業して間もない時、ついつい後回しになりがちな会計処理・事務作業。
特に一人や家族で事業をスタートした場合には、日頃の運営や営業活動に追われていまい、事務的業務まで気が回らないようになります。
結果として、現状業績の認識が半年後…などという事態に陥ります。
どんなに忙しくても、業務に追われていても、月次決算(売上と原価、経費の把握)は必須業務です。
経営・商売は打ち手の連続です。
打ち手は、刻一刻と変化していきます。その変化を見抜くためには、足元(自社・自店の業績現況)を把握しておくことが重要です。
ある起業家にヒアリングした際、「忙しくて事務的業務まで手が回らない」と言われていたので、その内容を伺いました。
すると、「販促のチラシを作ったり、イベント企画を立案したり、仕入れをしたり…」という話。
もちろん、その業務も大切です。しかし、いわゆる営業・販売・販促は、正しい現状認識の上に成り立ちます。
今、自社の営業利益はいくらか?原価率は適正か?無駄遣いはないか?資金繰りは大丈夫か?…などの現状認識が正しくされていないと、正しい戦略が立案できないのです。
月次の試算表に基づいた、業績振り返りと対策立案は、事業をスタートさせた当初は特に取り組むべき必須事項として認識しておきましょう。
起業して間もない時、ついつい後回しになりがちな会計処理・事務作業。
特に一人や家族で事業をスタートした場合には、日頃の運営や営業活動に追われていまい、事務的業務まで気が回らないようになります。
結果として、現状業績の認識が半年後…などという事態に陥ります。
どんなに忙しくても、業務に追われていても、月次決算(売上と原価、経費の把握)は必須業務です。
経営・商売は打ち手の連続です。
打ち手は、刻一刻と変化していきます。その変化を見抜くためには、足元(自社・自店の業績現況)を把握しておくことが重要です。
ある起業家にヒアリングした際、「忙しくて事務的業務まで手が回らない」と言われていたので、その内容を伺いました。
すると、「販促のチラシを作ったり、イベント企画を立案したり、仕入れをしたり…」という話。
もちろん、その業務も大切です。しかし、いわゆる営業・販売・販促は、正しい現状認識の上に成り立ちます。
今、自社の営業利益はいくらか?原価率は適正か?無駄遣いはないか?資金繰りは大丈夫か?…などの現状認識が正しくされていないと、正しい戦略が立案できないのです。
月次の試算表に基づいた、業績振り返りと対策立案は、事業をスタートさせた当初は特に取り組むべき必須事項として認識しておきましょう。
投稿日: 2018年9月24日 | 1:00 am