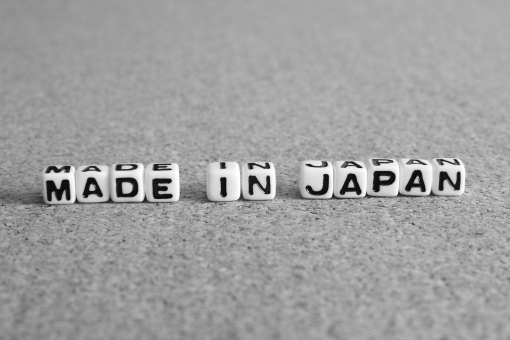中小企業診断士(経営コンサルタント)とデザイナー
経営コンサルタントという仕事は、つくづくクリエイティブ力が問われる…と感じる今日この頃です。
自分の直感や仮説、経験に基づくノウハウをいかに開発していくか?
常時、問題意識・課題意識を持つべきプロフェッショナルと言えます。
クリエイティブ・スキルこそ、他の士業の方々と差をつける重要なスキルファクターでしょう。
完全な未来創造型であり、クライアントから未来創造のお手伝いを期待されるのです。
クリエイティブスキルで勝負するという点では、デザイナーの方々と類似している点が多いと思っています。
違う点は、開発(クリエイト)したノウハウは、さらにグレードアップさせたり、カスタマイズさせたりすることで、他のクライアント様に役立てることができる点でしょうか?
ただ、ブランディング・マーケティング支援をクライアントで実行していくとき、デザイナーのヘルプやサポートは不可欠です。
「餅は餅屋」という言葉ある様に、それぞれの専門分野を結集して、ブランディングに向き合っていきます。
その際、ネットッワークを組む提携先のセレクトは留意しましょう。
「早い、腕がいい、ヒトがいい」この3つが必要条件です。
小生も、ブランディングメーケティング戦略支援の際に、よく相談するデザイナーがおられます。
彼は真摯に取り組んでくれるし、多様な相談に応じてくれます。
何より、現場に来てくれて同じ空気を吸いながら、情報共有や共感を求めてくれることに信頼感を持っています。
経営コンサルタントの連携先として、とっても重要な連携条件なんです。
経営コンサルタントという仕事は、つくづくクリエイティブ力が問われる…と感じる今日この頃です。
自分の直感や仮説、経験に基づくノウハウをいかに開発していくか?
常時、問題意識・課題意識を持つべきプロフェッショナルと言えます。
クリエイティブ・スキルこそ、他の士業の方々と差をつける重要なスキルファクターでしょう。
完全な未来創造型であり、クライアントから未来創造のお手伝いを期待されるのです。
クリエイティブスキルで勝負するという点では、デザイナーの方々と類似している点が多いと思っています。
違う点は、開発(クリエイト)したノウハウは、さらにグレードアップさせたり、カスタマイズさせたりすることで、他のクライアント様に役立てることができる点でしょうか?
ただ、ブランディング・マーケティング支援をクライアントで実行していくとき、デザイナーのヘルプやサポートは不可欠です。
「餅は餅屋」という言葉ある様に、それぞれの専門分野を結集して、ブランディングに向き合っていきます。
その際、ネットッワークを組む提携先のセレクトは留意しましょう。
「早い、腕がいい、ヒトがいい」この3つが必要条件です。
小生も、ブランディングメーケティング戦略支援の際に、よく相談するデザイナーがおられます。
彼は真摯に取り組んでくれるし、多様な相談に応じてくれます。
何より、現場に来てくれて同じ空気を吸いながら、情報共有や共感を求めてくれることに信頼感を持っています。
経営コンサルタントの連携先として、とっても重要な連携条件なんです。
投稿日: 2019年5月20日 | 11:00 pm