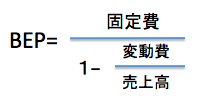中小企業診断士は稼げる資格である−12
中小企業診断士は、経営コンサルタントの国家資格ですが、難しい国家試験を突破してきたからといって万能のスーパーマンでありません。
時々、すべての経営課題を解決できるプロフェッショナル…という妄想を持たれている経営者に会います。
また、経営コンサルタントの中にも、「任せてください、私は失敗しませんから…!」と平気で言うコンサルタントも存在するから困ったものです。
何度も訴えていますが、中小企業診断士は万能のスーパーマンではありませんよ。絶対に!
根拠のないことを言い切ったり、何となくそんな感じがするという直感だけで提案するコンサルタントには要注意です(直感は全面否定する訳ではありません…念のため)。
中小企業診断士をはじめ、経営コンサルタントの中には、傾聴力のない輩もいます。
傾聴力というスキルはとても大切で、コンサルタントの中には”人の話を遮って(最後まで聴かないで)自分の意見を言う”輩もいます。
経営は人間力がモノを言います。人間の営みであり、人間を見つめることであり、人間の力を引き出すことが経営です。
経営者の声や幹部、社員、メンバーの声に耳を傾け、寄り添い(気持ちを同調させ)、共感し、最後まで言い分を受け止めて、最後に助言・アドバイスする…そんな忍耐強いスキルが求められます。
ときどき、話の途中で(勝手に思い込み)、自分の考えを一方的にぶつけるようなコンサルタントを散見しますが、そんな輩は最終的に経営者やメンバーから飽きられ嫌われ、コンサルティングの結果を出す前に契約解除されることになります。
中小企業診断士は、経営コンサルタントの国家資格ですが、難しい国家試験を突破してきたからといって万能のスーパーマンでありません。
時々、すべての経営課題を解決できるプロフェッショナル…という妄想を持たれている経営者に会います。
また、経営コンサルタントの中にも、「任せてください、私は失敗しませんから…!」と平気で言うコンサルタントも存在するから困ったものです。
何度も訴えていますが、中小企業診断士は万能のスーパーマンではありませんよ。絶対に!
根拠のないことを言い切ったり、何となくそんな感じがするという直感だけで提案するコンサルタントには要注意です(直感は全面否定する訳ではありません…念のため)。
中小企業診断士をはじめ、経営コンサルタントの中には、傾聴力のない輩もいます。
傾聴力というスキルはとても大切で、コンサルタントの中には”人の話を遮って(最後まで聴かないで)自分の意見を言う”輩もいます。
経営は人間力がモノを言います。人間の営みであり、人間を見つめることであり、人間の力を引き出すことが経営です。
経営者の声や幹部、社員、メンバーの声に耳を傾け、寄り添い(気持ちを同調させ)、共感し、最後まで言い分を受け止めて、最後に助言・アドバイスする…そんな忍耐強いスキルが求められます。
ときどき、話の途中で(勝手に思い込み)、自分の考えを一方的にぶつけるようなコンサルタントを散見しますが、そんな輩は最終的に経営者やメンバーから飽きられ嫌われ、コンサルティングの結果を出す前に契約解除されることになります。
投稿日: 2020年1月22日 | 10:55 pm