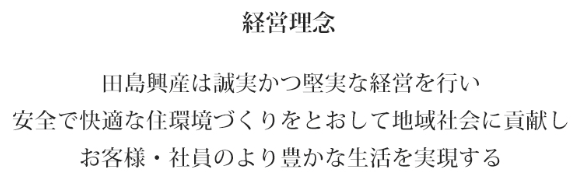社員(メンバー)の想いに向き合っていますか?
”強い(強固な)組織(チーム)を作りたい”という、組織強化のご相談を受けることがよくあります。相談を受ける時、抽象的な表現を具体化することからスタートします。
ヒアリングという手法を使います。なんだそういうことか…と思うなかれ。ヒアリングはプロの技です。
さておき、組織強化のための処方箋はあるのですが、経営者が求める”強い組織”を具体化すると様々な形態が浮かび上がってきます。
共通しているのは、モチベーションが高く、目的をしっかりと持ち、問題意識が高い組織…ということになるでしょう。
その場合自社が「どうして強い組織ではないのか?」を明確に探る必要があります。
そこで、リサーチが必要なわけです。
リサーチも様々なのですが、小生はよく”面談・ヒアリング”という手法を使います。
目安は一人当たり30分ほどです。
その構成メンバーの想いを明らかにして、モチベーション度合いを測定し、適材適所の人的配置の参考にします。
よく言われるのが、「経営者・幹部・上司が、自分の仕事を見てくれない」という不安に由来する不満。
経営者・幹部は、社員(メンバー)の現状や想いに向き合っていなければならない。
モチベーションが上がる環境を作り、環境を整え、環境に配置することがリーダーたる経営者の役目なのですから。
冷静に面談を遂行し、現状認識するためのヒアリングを実施する…そのためのサポーターとして我々のようなプロに依頼することも選択肢のひとつです。
”強い(強固な)組織(チーム)を作りたい”という、組織強化のご相談を受けることがよくあります。相談を受ける時、抽象的な表現を具体化することからスタートします。
ヒアリングという手法を使います。なんだそういうことか…と思うなかれ。ヒアリングはプロの技です。
さておき、組織強化のための処方箋はあるのですが、経営者が求める”強い組織”を具体化すると様々な形態が浮かび上がってきます。
共通しているのは、モチベーションが高く、目的をしっかりと持ち、問題意識が高い組織…ということになるでしょう。
その場合自社が「どうして強い組織ではないのか?」を明確に探る必要があります。
そこで、リサーチが必要なわけです。
リサーチも様々なのですが、小生はよく”面談・ヒアリング”という手法を使います。
目安は一人当たり30分ほどです。
その構成メンバーの想いを明らかにして、モチベーション度合いを測定し、適材適所の人的配置の参考にします。
よく言われるのが、「経営者・幹部・上司が、自分の仕事を見てくれない」という不安に由来する不満。
経営者・幹部は、社員(メンバー)の現状や想いに向き合っていなければならない。
モチベーションが上がる環境を作り、環境を整え、環境に配置することがリーダーたる経営者の役目なのですから。
冷静に面談を遂行し、現状認識するためのヒアリングを実施する…そのためのサポーターとして我々のようなプロに依頼することも選択肢のひとつです。
投稿日: 2020年2月2日 | 10:38 am