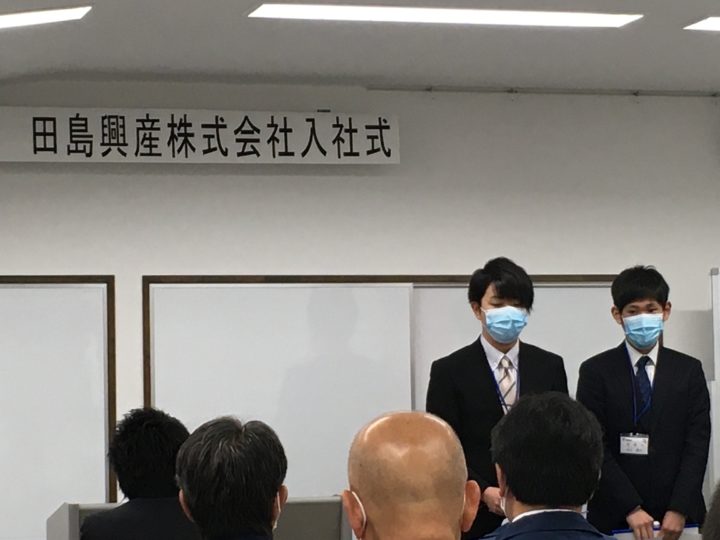理と利の統合…。
理と利とは「理=理念、経営理念」、「利=利益」のことを指します。
最強の企業文化確立手法『理念経営』に立ち向かう時、この課題にぶつかってしまうことがよくあります。理念経営の本質は、「理念を体現する企業運営を確立する」ことであり、決して「理念を掲げて唱和する」だけのようなチープなものではありません。
朝礼や会議では、経営理念やクレドを”元気よく”唱和していても、実際の業務遂行の際には”全く違う(理念に反する)言動”をしている企業経営は、よく見られる現象です。
はっきり申し上げますが、理念と利益はセパレート(並列)ではありません。直列です。「理念経営を組織の隅々まで浸透させ、メンバーの判断基準・言動基準として確立された際に、その結果成果として「利益」がもたらされるのです。
それだけ、理念経営は難しい…。しかし、中小企業経営の目指すべき本当に価値ある取り組みなのです。
「経営理念は掲げたけれど…それはただの標語にしか過ぎない。」
「経営理念は、社員の意識を統一するための、ただのフレーズである。」
「経営理念ってうちの会社にあったの?」(受け取った名刺に立派に記載されてありましたが…。)
実際に聞いた、とある中小企業の経営者、社員の発言事例です。
どれもすべて間違い。
経営理念に明記されている文言(フレーズ)が、すべての構成員の「価値判断基準、言動基準」となっていますか?
「業績目的経営」は、判断基準が損得になりがち。「理念目的経営」は、判断基準が善悪判断になります。
損得判断経営は、いつの日か行き詰まります。なぜなら「誰かを犠牲にする経営」になってしまうからです。
理と利とは「理=理念、経営理念」、「利=利益」のことを指します。
最強の企業文化確立手法『理念経営』に立ち向かう時、この課題にぶつかってしまうことがよくあります。理念経営の本質は、「理念を体現する企業運営を確立する」ことであり、決して「理念を掲げて唱和する」だけのようなチープなものではありません。
朝礼や会議では、経営理念やクレドを”元気よく”唱和していても、実際の業務遂行の際には”全く違う(理念に反する)言動”をしている企業経営は、よく見られる現象です。
はっきり申し上げますが、理念と利益はセパレート(並列)ではありません。直列です。「理念経営を組織の隅々まで浸透させ、メンバーの判断基準・言動基準として確立された際に、その結果成果として「利益」がもたらされるのです。
それだけ、理念経営は難しい…。しかし、中小企業経営の目指すべき本当に価値ある取り組みなのです。
「経営理念は掲げたけれど…それはただの標語にしか過ぎない。」
「経営理念は、社員の意識を統一するための、ただのフレーズである。」
「経営理念ってうちの会社にあったの?」(受け取った名刺に立派に記載されてありましたが…。)
実際に聞いた、とある中小企業の経営者、社員の発言事例です。
どれもすべて間違い。
経営理念に明記されている文言(フレーズ)が、すべての構成員の「価値判断基準、言動基準」となっていますか?
「業績目的経営」は、判断基準が損得になりがち。「理念目的経営」は、判断基準が善悪判断になります。
損得判断経営は、いつの日か行き詰まります。なぜなら「誰かを犠牲にする経営」になってしまうからです。
投稿日: 2020年4月3日 | 9:49 pm