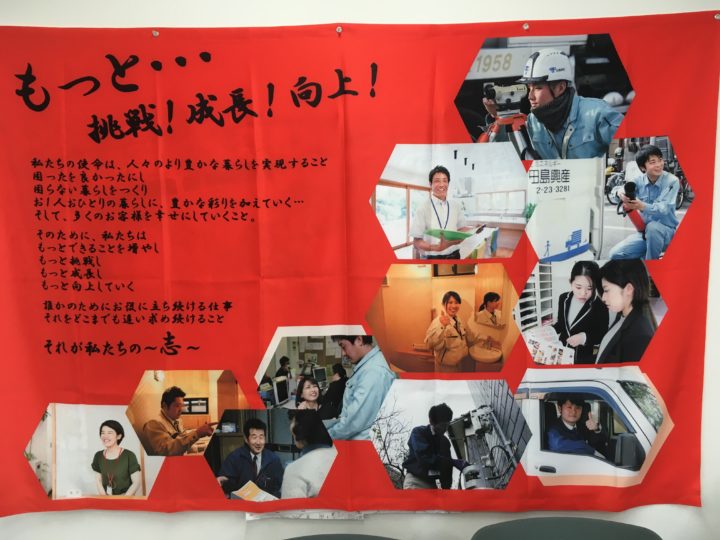大変革期を機会(チャンス)と捉える…。
コロナウィルスの現状が、連日報道されている今日。この状況はいつまで続くのか…ということを考えるよりも、今できること・今しかできないことを考えて実行していくことが大切です。
世の中の出来事、そして自分の身に降りかかる出来事は”偶然”ではなく”必然”なのです。経営者たる社会のリーダーは、プラス思考・ポジティブシンキングを約束しなければなりません。
今まさに、この時世を「大変革期の機会(チャンス)」と捉えて種々様々な戦略を考案し、立案し、実行していく時です。
社会の出来事、政府の対応や経済対策…外部的な環境は、自力では如何ともしがたい要因です。
であるならば、自らの企業経営をこれからどうしていくか…?を前向きに考えていくことが価値ある取り組みと言えます。
何度も訴えていますが、まずは資金確保を徹底してください。そのためには、政府が打ち出した緊急融資などを遠慮なく活用することが大切です。
このような時こそ、普段しっかりとした経営管理をしているか…。管理がしっかりしている企業には、金融機関は融資にしっかりと向き合ってくれるでしょう。
逆に、散財癖のある経営者、借入金に依存している経営者、毎年赤字を計上している経営者には、大変厳しい現実が立ちはだかるでしょう。
だからこそ声を大にして言いたいのです。今こそ経営の足元を見つめ直す時です…と。
”正しい経営は滅びない!”とは、恩師・坂本光司先生の言葉。
まさに正しい経営とは何か?をじっくりと考え、”いい会社になるための経営”に思い切って舵を切る時です。
コロナウィルスの現状が、連日報道されている今日。この状況はいつまで続くのか…ということを考えるよりも、今できること・今しかできないことを考えて実行していくことが大切です。
世の中の出来事、そして自分の身に降りかかる出来事は”偶然”ではなく”必然”なのです。経営者たる社会のリーダーは、プラス思考・ポジティブシンキングを約束しなければなりません。
今まさに、この時世を「大変革期の機会(チャンス)」と捉えて種々様々な戦略を考案し、立案し、実行していく時です。
社会の出来事、政府の対応や経済対策…外部的な環境は、自力では如何ともしがたい要因です。
であるならば、自らの企業経営をこれからどうしていくか…?を前向きに考えていくことが価値ある取り組みと言えます。
何度も訴えていますが、まずは資金確保を徹底してください。そのためには、政府が打ち出した緊急融資などを遠慮なく活用することが大切です。
このような時こそ、普段しっかりとした経営管理をしているか…。管理がしっかりしている企業には、金融機関は融資にしっかりと向き合ってくれるでしょう。
逆に、散財癖のある経営者、借入金に依存している経営者、毎年赤字を計上している経営者には、大変厳しい現実が立ちはだかるでしょう。
だからこそ声を大にして言いたいのです。今こそ経営の足元を見つめ直す時です…と。
”正しい経営は滅びない!”とは、恩師・坂本光司先生の言葉。
まさに正しい経営とは何か?をじっくりと考え、”いい会社になるための経営”に思い切って舵を切る時です。
投稿日: 2020年4月23日 | 9:19 pm