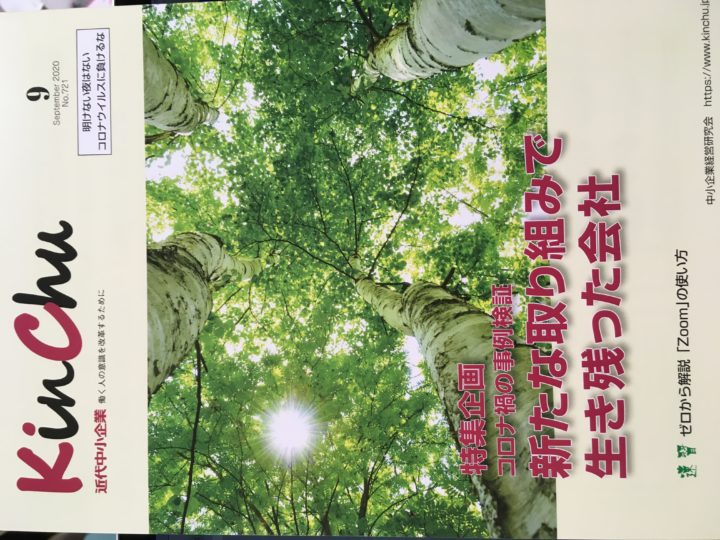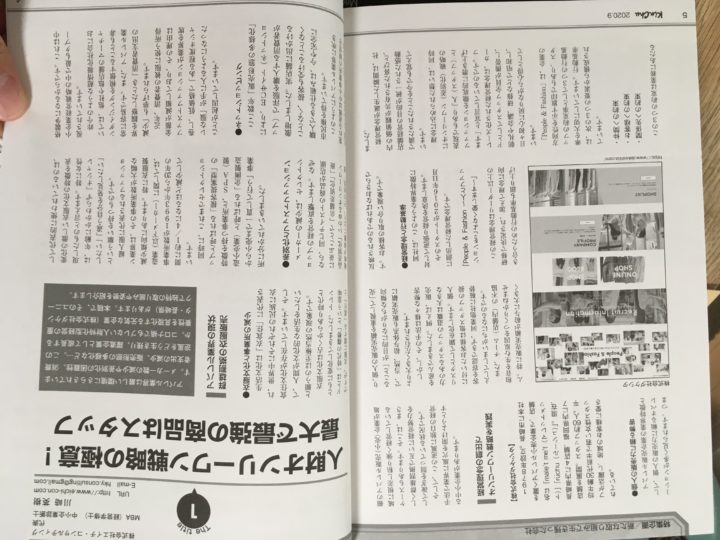道、とおき道 〜中小企業診断士の道しるべ〜
「この道より、我を生かす道なし。この道を歩く」(武者小路実篤)…。経営コンサルタントとして活動して、延15年。中小企業診断士として13年目に入りました。ただひたすらに、コンサルティングとクライアントの繁栄に注力して走った日々。
「この道より、我を生かす道なし。この道を歩く」という言葉が、身にしみて感じられる今日この頃です。
以前、「私は失敗したことはありません。」と宣う自称経営コンサルタントがいました。明確に断言できますが、十戦全勝という経営コンサルタントはこの世に存在しません。
うまくいくこと、うまくいかないこと…うまくいかない時に「どうするか?」を考え、次の手を打つ準備や提案をするのがプロのコンサルタントの使命でしょう。
もしも「経営コンサルティング道」という言葉があるとすれば、まさに”「道、とおき道」だなあ”と思う今日この頃です。
幸い、小生には敬愛すべき経営コンサルタントの先輩に恵まれました。諸先輩方は、どの人も人間として尊敬でき、コンサルティングのマインドやスキル、知識において「まだまだ太刀打ちできない領域におられる」方々です。
先輩方は「中小企業診断士」の国家資格を持ってる方ではありません。
プロの経営コンサルタントとして、自らの知識やスキル、ノウハウで勝負されている方々です。中小企業診断士として、国家から付与された資格を持って看板としている以上、その価値をもっともっと高めたい…そんな想いを強めて、「中小企業診断士のマインドセットーARIKATA」を綴っています。
全国で2万人と言われる中小企業診断士が、もっと中小企業の経営の現場に寄り添い、課題解決に奔走する…。小生の活動が、そんな道しるべでありたい…と願っています。
「この道より、我を生かす道なし。この道を歩く」(武者小路実篤)…。経営コンサルタントとして活動して、延15年。中小企業診断士として13年目に入りました。ただひたすらに、コンサルティングとクライアントの繁栄に注力して走った日々。
「この道より、我を生かす道なし。この道を歩く」という言葉が、身にしみて感じられる今日この頃です。
以前、「私は失敗したことはありません。」と宣う自称経営コンサルタントがいました。明確に断言できますが、十戦全勝という経営コンサルタントはこの世に存在しません。
うまくいくこと、うまくいかないこと…うまくいかない時に「どうするか?」を考え、次の手を打つ準備や提案をするのがプロのコンサルタントの使命でしょう。
もしも「経営コンサルティング道」という言葉があるとすれば、まさに”「道、とおき道」だなあ”と思う今日この頃です。
幸い、小生には敬愛すべき経営コンサルタントの先輩に恵まれました。諸先輩方は、どの人も人間として尊敬でき、コンサルティングのマインドやスキル、知識において「まだまだ太刀打ちできない領域におられる」方々です。
先輩方は「中小企業診断士」の国家資格を持ってる方ではありません。
プロの経営コンサルタントとして、自らの知識やスキル、ノウハウで勝負されている方々です。中小企業診断士として、国家から付与された資格を持って看板としている以上、その価値をもっともっと高めたい…そんな想いを強めて、「中小企業診断士のマインドセットーARIKATA」を綴っています。
全国で2万人と言われる中小企業診断士が、もっと中小企業の経営の現場に寄り添い、課題解決に奔走する…。小生の活動が、そんな道しるべでありたい…と願っています。
投稿日: 2020年9月15日 | 10:09 pm