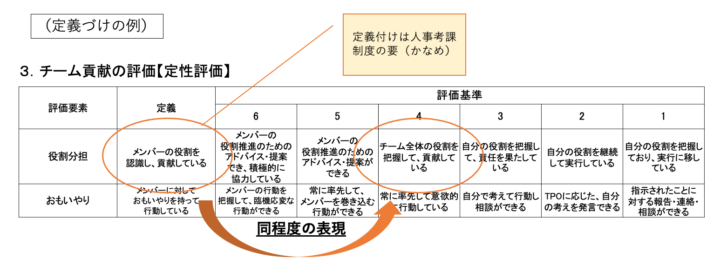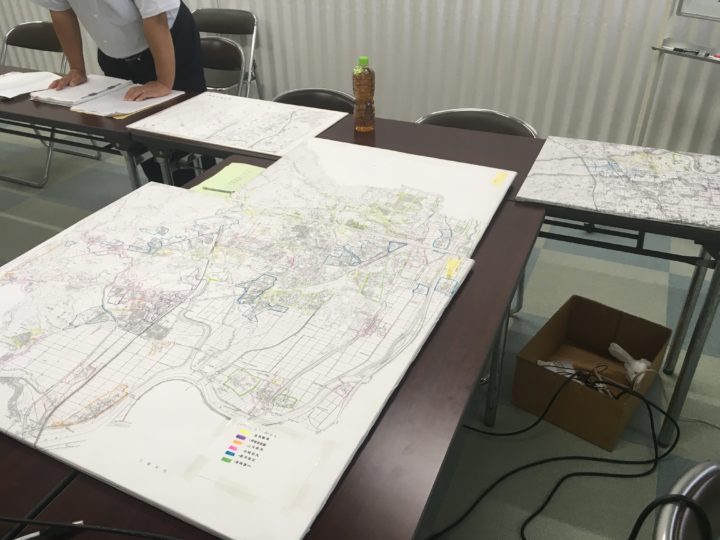中小企業経営における、”いまどき”の営業戦略
あるクライアントの社長(60代)と打ち合わせしていた時…。「一昔前と、営業展開に関する価値観が全く変わったよね。」という話になりました。そう言われてみれば、全くその通りです。およそ四半世紀前。僕が、放送局の営業部員だったころ。営業スタイルは完全にプッシュ型でした。
スポンサー先に訪問し、企画書をプレゼンテーションし、場合によっては価格調整で決定にいたるプロセスです。
もちろん、現在でもそのスタイルは生き続けています。しかし、”いまどき”の営業戦略は、完全にプル型に主導権が移りました。つまり、お客様の方から”その商品が欲しい”と思われるような営業・販売戦略を、いかに確立できるか?が勝敗を分けるようになったのです。
ここで問われるのは、各営業スタッフや販売員の”点の力”ではありません。企業全体で、ブランディングを確立していく”面の力”です。
ですので、ますますマーケティングという発想がとても大切です。データや傾向、そして現場(お客様)の生の声などを共有・分析し、これからの営業活動に活かしていく”戦略型営業”です。もはや3Kと呼ばれる「勘、経験、根性」の営業スタイルは完全に時代遅れとなりました。
営業担当部署、ひいては企業全体として”プル型”営業戦略に挑戦する時代と言えましょう。
営業部署のミッションは、”稼ぐ”ことから「企業努力や企業価値、企業全体の”想い”を伝え、結果的業績を創り出す」という概念に姿を変えたのです。
あるクライアントの社長(60代)と打ち合わせしていた時…。「一昔前と、営業展開に関する価値観が全く変わったよね。」という話になりました。そう言われてみれば、全くその通りです。およそ四半世紀前。僕が、放送局の営業部員だったころ。営業スタイルは完全にプッシュ型でした。
スポンサー先に訪問し、企画書をプレゼンテーションし、場合によっては価格調整で決定にいたるプロセスです。
もちろん、現在でもそのスタイルは生き続けています。しかし、”いまどき”の営業戦略は、完全にプル型に主導権が移りました。つまり、お客様の方から”その商品が欲しい”と思われるような営業・販売戦略を、いかに確立できるか?が勝敗を分けるようになったのです。
ここで問われるのは、各営業スタッフや販売員の”点の力”ではありません。企業全体で、ブランディングを確立していく”面の力”です。
ですので、ますますマーケティングという発想がとても大切です。データや傾向、そして現場(お客様)の生の声などを共有・分析し、これからの営業活動に活かしていく”戦略型営業”です。もはや3Kと呼ばれる「勘、経験、根性」の営業スタイルは完全に時代遅れとなりました。
営業担当部署、ひいては企業全体として”プル型”営業戦略に挑戦する時代と言えましょう。
営業部署のミッションは、”稼ぐ”ことから「企業努力や企業価値、企業全体の”想い”を伝え、結果的業績を創り出す」という概念に姿を変えたのです。
投稿日: 2020年11月5日 | 9:26 pm