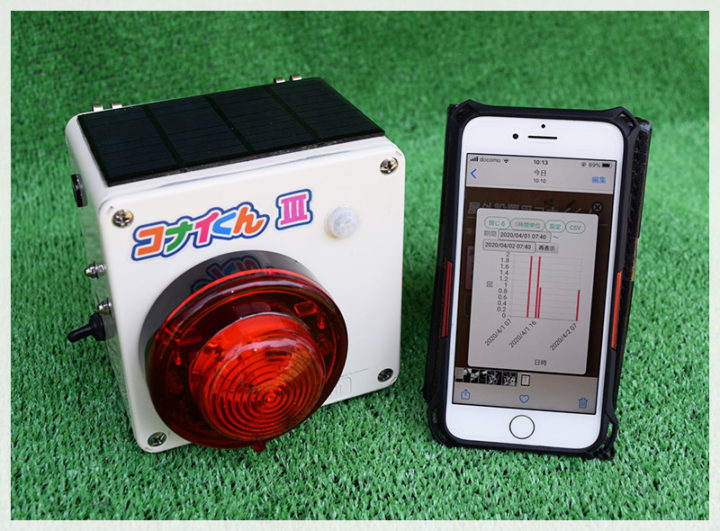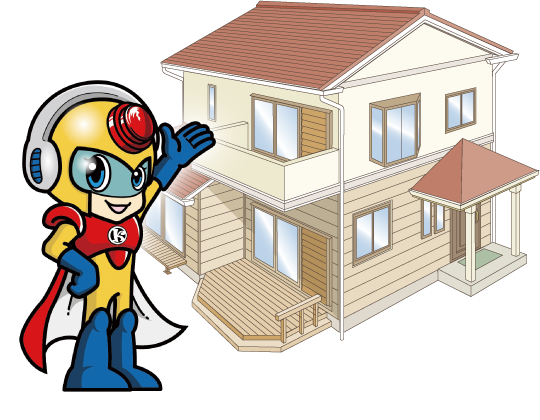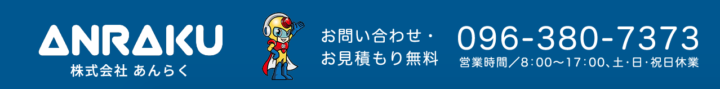商売を知らない人のための商売の話ー2
「商売(経営)は”やり方”が重要なのでなく、”あり方”が問われる営みである」。この言葉は、法政大学大学院時代の恩師の言葉から引用したものです。何事も動機が大切で、僕のような仕事をしていると「この人は商売がうまくいくな…」とか、逆に「かなりご苦労されそうだな…」などと、経験による独特の臭いを感じるようになります。
そして、その直感はかなりの確率で当たります。まさに、「あり方=マインドやハートといった想いに裏付けされた商売の姿勢」が分水嶺となるのです。
経営のノウハウは、勉強すれば身に付けることができます。しかし、ノウハウに頼ってしまうとテクニックに走った商売になってしまいます。商売で最も大切なのは、従業員目線とお客様目線そして(仕入れ先などの)関係先目線に合わせた運営をすること…です。最も大切なのは、Win-Win-Winの三方良し経営です。
もう一つ、商売はお客様からお金をいただきますよね。何かをお金に変えているわけです。「何をお金に変えていますか?」という問いをセミナーなどで参加者に尋ねると、「???」という反応をされる方がほとんど。
お金に交換しているのは、商品ではありません。商品というのは、商売をする人の”想い”を形にしたものに過ぎない。”想い”というのは、商売人の努力や頑張りのことです。いわゆる「価値(Value)」と呼ばれるものです。
「価値をお客様に届けて、お金をいただく行為」これが商売の本質です。
ビジネスモデルの作り方、マーケティング戦略の立て方、事業計画の立て方…もちろん大切でしょう。
その前に…学ぶべき「商人(あきんど)学」というものがあるのです。
「商売(経営)は”やり方”が重要なのでなく、”あり方”が問われる営みである」。この言葉は、法政大学大学院時代の恩師の言葉から引用したものです。何事も動機が大切で、僕のような仕事をしていると「この人は商売がうまくいくな…」とか、逆に「かなりご苦労されそうだな…」などと、経験による独特の臭いを感じるようになります。
そして、その直感はかなりの確率で当たります。まさに、「あり方=マインドやハートといった想いに裏付けされた商売の姿勢」が分水嶺となるのです。
経営のノウハウは、勉強すれば身に付けることができます。しかし、ノウハウに頼ってしまうとテクニックに走った商売になってしまいます。商売で最も大切なのは、従業員目線とお客様目線そして(仕入れ先などの)関係先目線に合わせた運営をすること…です。最も大切なのは、Win-Win-Winの三方良し経営です。
もう一つ、商売はお客様からお金をいただきますよね。何かをお金に変えているわけです。「何をお金に変えていますか?」という問いをセミナーなどで参加者に尋ねると、「???」という反応をされる方がほとんど。
お金に交換しているのは、商品ではありません。商品というのは、商売をする人の”想い”を形にしたものに過ぎない。”想い”というのは、商売人の努力や頑張りのことです。いわゆる「価値(Value)」と呼ばれるものです。
「価値をお客様に届けて、お金をいただく行為」これが商売の本質です。
ビジネスモデルの作り方、マーケティング戦略の立て方、事業計画の立て方…もちろん大切でしょう。
その前に…学ぶべき「商人(あきんど)学」というものがあるのです。
投稿日: 2020年11月18日 | 10:55 pm