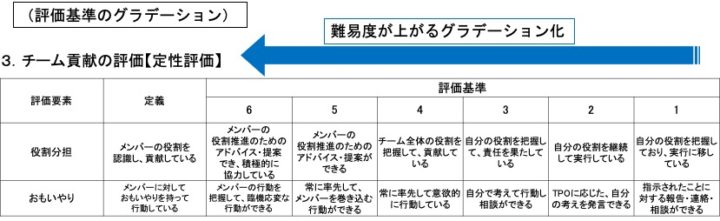”やり方”や”手法”といった方法論に惑わされない…。
書店のコーナーに立ち並ぶ、様々なビジネス書の数々。本当に多くの書籍が立ち並んでいますよね。
大手コンサルティング会社が出版したものから、まだまだこれからという方々が書かれた書籍まで、種々様々です。仕事柄、必ずチェックするコーナーではありますが、正直「読むに値しない本が多いな…」と思います。もちろん、方法や手法は学ぶに値しますよ、念のため。ただし、表題に「絶対成功する◯◯」とか「必ず売れる◯◯」といったタイトルが書かれている本は、絶対にお勧めしません。
ビジスネ書で読むに値する本は、選んだ方がいいというのが、僕の結論です。ただでさえ、忙しい中です。効率的・効果的に知識の蓄積をしていきたいですよね。
一番おすすめできるビジネス書のタイプは、「実例に基づいた物語」そして「経済小説」(フィクションでいい)です。
経済小説?と思う人もいると思いますが、そこに書かれている喜怒哀楽物語は、コンサルティング・プレゼンや講演講師のレクチャー時に大いに役立ちます。
僕もビジネス書を書きますが、できるだけ「成功例・失敗例」といった事例に基づいた経験談を執筆します。
あるべき論は机上の空論であり、三現主義(現地、現実、現物)とはかけ離れた内容になる場合が多い。そして、ノウハウに頼るようなコンサルティングは、クライアントから見透かされます。経営も然り、テクニックに走る経営はお客様から見透かされます。
大事なのは、何事もハート(心)、情熱です。熱意(エネルギー)と言ってもいいでしょう。
よく、精神論だけでは戦えないと言いますよね。当然です。超越した情報化社会の今日、コンサルティングも経営も精神論だけでは勝てません。
しかし、「精神論だけでは戦えませんが、精神論がないと戦えない」のも真実です。
ですので、書店に行ってビジネス書を探索するときは、あるべき・テクニック・方法…を列挙した書籍は避けましょう。
露骨に模倣するつもりなら話は別ですが。プロコンならば、ノウハウは自分で開発していきたいものです。
書店のコーナーに立ち並ぶ、様々なビジネス書の数々。本当に多くの書籍が立ち並んでいますよね。
大手コンサルティング会社が出版したものから、まだまだこれからという方々が書かれた書籍まで、種々様々です。仕事柄、必ずチェックするコーナーではありますが、正直「読むに値しない本が多いな…」と思います。もちろん、方法や手法は学ぶに値しますよ、念のため。ただし、表題に「絶対成功する◯◯」とか「必ず売れる◯◯」といったタイトルが書かれている本は、絶対にお勧めしません。
ビジスネ書で読むに値する本は、選んだ方がいいというのが、僕の結論です。ただでさえ、忙しい中です。効率的・効果的に知識の蓄積をしていきたいですよね。
一番おすすめできるビジネス書のタイプは、「実例に基づいた物語」そして「経済小説」(フィクションでいい)です。
経済小説?と思う人もいると思いますが、そこに書かれている喜怒哀楽物語は、コンサルティング・プレゼンや講演講師のレクチャー時に大いに役立ちます。
僕もビジネス書を書きますが、できるだけ「成功例・失敗例」といった事例に基づいた経験談を執筆します。
あるべき論は机上の空論であり、三現主義(現地、現実、現物)とはかけ離れた内容になる場合が多い。そして、ノウハウに頼るようなコンサルティングは、クライアントから見透かされます。経営も然り、テクニックに走る経営はお客様から見透かされます。
大事なのは、何事もハート(心)、情熱です。熱意(エネルギー)と言ってもいいでしょう。
よく、精神論だけでは戦えないと言いますよね。当然です。超越した情報化社会の今日、コンサルティングも経営も精神論だけでは勝てません。
しかし、「精神論だけでは戦えませんが、精神論がないと戦えない」のも真実です。
ですので、書店に行ってビジネス書を探索するときは、あるべき・テクニック・方法…を列挙した書籍は避けましょう。
露骨に模倣するつもりなら話は別ですが。プロコンならば、ノウハウは自分で開発していきたいものです。
投稿日: 2020年12月10日 | 10:56 pm