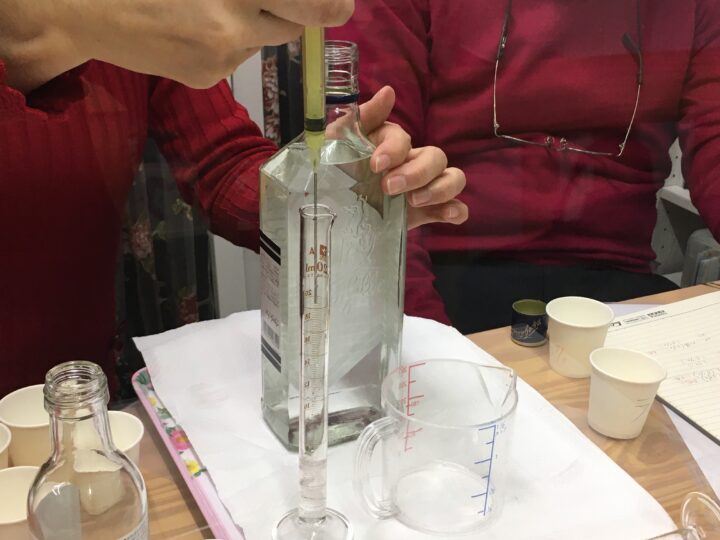コンサルティングは引き寄せの法則が作用している?
中小企業診断士として、現場で経営コンサルティングを実践していると、引き寄せの法則が作用しているのかな…と感じることが多くあります。
独立して、クライアントを選ぶようになると特に”引き寄せ”を考えるようになりました。具体的にいうと、同じ思考や価値観のクライアント様とのご縁が多くなりましたね。圧倒的に…。
確かに、引き寄せの法則は存在すると思っています。僕自身ポジティブ思考人間ですから、ネガティブな思考の経営者や会社とはなかなかご縁がありません。また、社員を大切にする価値観を主張していますから、社員を大切にしない会社とは仕事のご縁がなくなりました。
そして、企業経営にも同じことがあると考えています。
類は友を呼ぶ…とはよく言ったものです。
会社の社風や価値観は、同じ雰囲気や価値観を持った社員やお客様を呼び寄せます。また、違う雰囲気や価値観を持った社員は、早晩会社を去りますし、お客様も離れていく傾向にあります。
経営コンサルティングというのは、ある意味、”良好な引き寄せの法則”を構築するミッションなのかも知れません。
コンサルタント同士でもそうだと思います。経営コンサルティングにも、実に様々な価値観があります。
「企業経営は業績が全て」です「儲け方教えます」というコンサルタント(これが本当にできるどうかは別ですよ。笑)同士は、そのネットワークを作りはじめます。
コンサルティングを、「上から目線で弱みばかりを苦言・指摘する」仕事だと勘違いしている輩もいますが、このような方々同士でご縁があるでしょう。
引き寄せの法則も、こうやって考えると、やっぱり作用するのだなと考えてしますのです。
中小企業診断士として、現場で経営コンサルティングを実践していると、引き寄せの法則が作用しているのかな…と感じることが多くあります。
独立して、クライアントを選ぶようになると特に”引き寄せ”を考えるようになりました。具体的にいうと、同じ思考や価値観のクライアント様とのご縁が多くなりましたね。圧倒的に…。
確かに、引き寄せの法則は存在すると思っています。僕自身ポジティブ思考人間ですから、ネガティブな思考の経営者や会社とはなかなかご縁がありません。また、社員を大切にする価値観を主張していますから、社員を大切にしない会社とは仕事のご縁がなくなりました。
そして、企業経営にも同じことがあると考えています。
類は友を呼ぶ…とはよく言ったものです。
会社の社風や価値観は、同じ雰囲気や価値観を持った社員やお客様を呼び寄せます。また、違う雰囲気や価値観を持った社員は、早晩会社を去りますし、お客様も離れていく傾向にあります。
経営コンサルティングというのは、ある意味、”良好な引き寄せの法則”を構築するミッションなのかも知れません。
コンサルタント同士でもそうだと思います。経営コンサルティングにも、実に様々な価値観があります。
「企業経営は業績が全て」です「儲け方教えます」というコンサルタント(これが本当にできるどうかは別ですよ。笑)同士は、そのネットワークを作りはじめます。
コンサルティングを、「上から目線で弱みばかりを苦言・指摘する」仕事だと勘違いしている輩もいますが、このような方々同士でご縁があるでしょう。
引き寄せの法則も、こうやって考えると、やっぱり作用するのだなと考えてしますのです。
投稿日: 2021年2月26日 | 9:51 pm